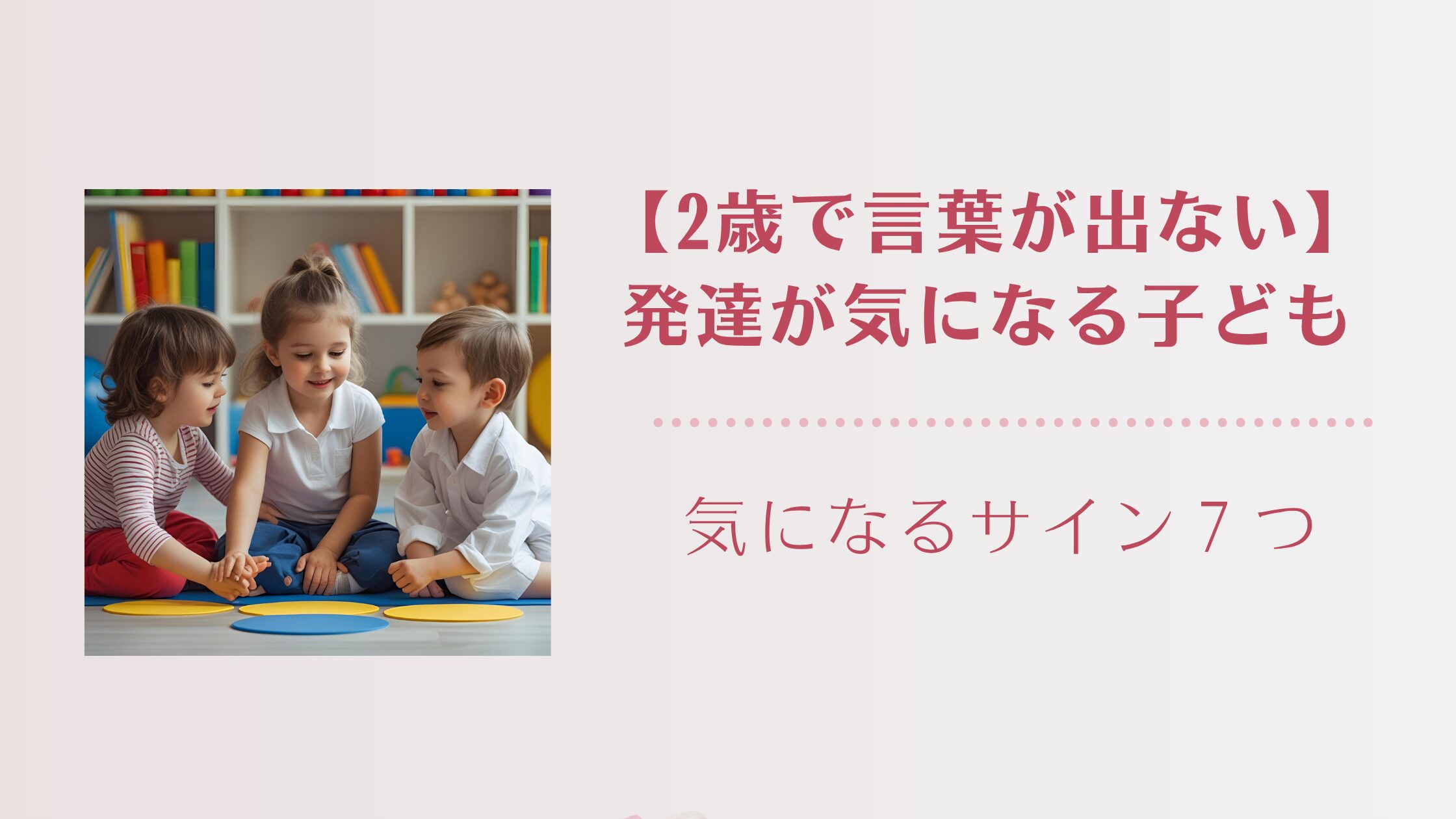「2歳になっても意味のある言葉が出ていない」「うちの子、あんまりしゃべらないかも…」
周りの子と比べて不安になったり、育て方が悪かったのかと悩んだりしていませんか?
わが家でも、息子が2歳を過ぎても単語が増えず、他の子と少し違うかも…と感じるようになりました。とはいえ、誰かに相談するほどではない気もして、もやもやと悩む日々が続いていました。
ただ、「ちょっと気になる…」という小さな違和感は、親だからこそ気づけるサインかもしれません。
この記事では、私自身が振り返って「これがサインだったかもしれない」と思う7つの気になる行動を紹介します。
今、同じように悩んでいるママやパパの参考になれば嬉しいです。
【チェックリスト】2歳の子に見られる“気になるサイン”7つ
子どもの発達は一人ひとり違いますが、言葉の遅れや発達の特性がある場合、早くから見られる行動があります。ここでは、私が当時「気づいておけばよかった」と思った7つのサインをご紹介します。
① 意味のある言葉が出ない・2語文が出ない
2歳を過ぎても「まんま」「ブーブー」など、1語発語で意味のある単語がほとんど聞かれない状態が続いていませんか?
2歳前後では、単語の数が増え、2語文(「ママ きた」など)を話すようになる子もいます。言葉が少ない場合、聞き取りや発語の力だけでなく、コミュニケーションの土台に注目することも大切です。
我が家では…
息子は「んーん」「うー」などの喃語は多かったものの、意味のある言葉として定着するまでに時間がかかりました。2歳終わり頃に「あお」とふわっと発語するようになりました。その後「ばなな」を「ぱ(ば)」、りんごを「り」というなど、単語を一文字で表すような表現(パーシャルワード)は少しずつ増えていましたが、2語文はほど遠い気がしました。
② 指差しや真似が少ない
子どもが「見て見て!」と指をさして、大人と一緒に何かを共有する姿。これが「共同注意」と呼ばれる大事な発達のサインです。
絵本を読んでいるときに「わんわん、どこかな?」と聞いて、子どもがその動物を指さしてくれる場面。これが、言葉を理解し、伝えようとする力の土台になります。
また、親の真似をして掃除や電話のふりをする「ごっこ遊び」も、人との関わりや意図を理解する力につながり、社会性が育っていきます。
社会性やコミュニケーションへの関心が育っているか、小さなやり取りがとても大切です。
我が家では…
息子は自らの「指差し」は多くみられませんでした。他人が「指差し」した場合、その方向ではなく自分の興味があるものに目線を送っていました。「真似っこ」を促しても、違うところを見たり、きょとんとしていることも。
③ 呼びかけへの反応が薄い
家族の声や生活音には反応するのに、こちらが呼びかけたり、何かを話しかけても目をそらしたまま…そんな場面が多くありませんか?
もちろん、遊びに夢中で気づかないこともありますが、「何度呼んでも反応がない」「目が合いづらい」と感じる場合は要注意。
「もしかして耳が聞こえない?」と心配になるかもしれませんが、聞こえていても人との関わりに関心が向きづらい状態かもしれません。音には気づいていても、人の呼びかけに注意を向けにくいタイプの子がいることを知りました。
我が家では…
名前を呼んでも無反応。目の前に立ったりして彼の視界に入るようにしたり、目の前で手を振ってアピールするとようやく気づく…ということがよくありました。
④ 視線が合いにくい・共感的な反応が少ない
「目と目が合う」体験。成長とともに、嬉しいことがあると「ねえ見て!」と視線を送ってきたり、こちらが笑うと一緒に笑ったりと、自然な共感が育まれていきます。でもそんな仕草があまり見られない。
喜びや驚きを共有するようなアイコンタクトが少ないと、親子のコミュニケーションにズレが生まれやすくなります。
子供からの投げかけがいつかあるかもと願いながら、私の方から何度も目線を合わせに行ったり、大便を意識しながら共感もしてきました。
我が家では…
おもちゃで楽しく遊んでいても、私をはじめ周りの子どもたちを見ることがほとんどありませんでした。積み木を高く積めたときに「すごいね!」と声をかけても、積み木自体をじっと眺めたり、並べてみたり、ひとりで”もの”のと向き合うことに集中しているよう。「褒められて嬉しい」という反応が薄いなと感じることが何度かありました。
⑤ おもちゃの遊び方が独特・繰り返し遊びが多い
ブロックを並べる、タイヤをくるくる回す、同じ動作を繰り返す…。
一見すると楽しそうな遊びも、「型にはまった繰り返し」「意味のある遊びにつながりにくい」ようであれば、気になるサインになることがあります。
興味の偏りや感覚の敏感さが関係して「感覚のこだわり」や「見立て遊びの発達段階の違い」が表れることもあります。
我が家では…
ブロックや積み木を積むのではなく、ひたすら横に並べる。クレヨンをケースに書いてある並び順でケースの外でひたすら並べる。お店屋さんごっこをすると、すべての商品をボタンに通さないと気が済まない。などの行動が見られました。
⑥ 人とのやりとりが続かない(家庭での様子)
言葉の発達には、「相手に伝えたい・相手の言葉に応えたい」という気持ちのやりとりが大切です。
呼びかけに一度は反応しても、その後のやり取りが続かない、共感的な返しがない場合も、コミュニケーションの発達が気になるサインです。
一方的に話すことはあっても、相手の言葉を待ったり応じたりするのが苦手な子もいます。
これは言語面だけでなく、社会性や注意の向け方が影響している場合もあるため、日々のやりとりの中で少し意識して見てみると良いかもしれません。
我が家では…
声をかけても反応が薄く、返事だけで終わってしまいました。質問をしても「うん」「いや」など単語でしか返さない。会話を広げようとしても、あまり続かない。
⑦お友達との関わりが少ない(園や外出先での様子)
遊びの中で他の子と関わることが少なく、「ひとりで集中して遊んでいる時間が長い」「関わろうとしてもすぐ離れてしまう」と感じたことはありませんか?
もちろん一人遊びが好きな子もいますが、人とのやりとりが自然に続かないときは、発達面でのサインとなることがあります。集団での関わり方に難しさを感じているかもしれません。
我が家では…
公園でもお友だちには目もくれず、ひとりでずっとすべり台を繰り返すような遊び方をしていました。
他の子が近づいてくると、気が付いていないのか、違う場所に行ってしまうこともありました。
7つのサインまとめ
【2歳児の発達が気になったら見てほしい7つのサイン】
| サイン | 内容 | 具体的な様子・気になるポイント |
|---|---|---|
| ① 言葉が出ない・2語文が出ない | 「ママ、きた」などの2語文が出にくい | 使う言葉の数が非常に少ない |
| ② 指差し・模倣が少ない | アレなあに?の指差し、まねっこが見られない | 拍手やバイバイのまねをしない |
| ③ 呼びかけの反応が薄い | 名前を呼んでも無視・振り向かない | 他の音には反応することがある |
| ④ 視線が合いにくい・共感が少ない | 表情の共有が少ない | アイコンタクトが取れない |
| ⑤ おもちゃの遊び方が独特・繰り返し遊びが多い | 並べる、回すなど遊びが偏る | |
| ⑥ 人とのやりとりが続かない(家庭での様子) | 一言で終わり、会話のキャッチボールにならない | 質問に答えない、話が広がらない |
| ⑦ お友だちとの関わりが極端に少ない(園や外出先での様子) | お友だちに興味がない・集団遊びに加わらない | 声をかけても反応が薄い |
言葉の遅れが気になるとき、相談先は?どうすればいい?
私自身も、はじめは不安でいっぱいでしたが、相談する中で「子どもに合った関わり方」が少しずつ見えてきました。早めに動くことで、親の不安が減るだけでなく、子どもの力を引き出すきっかけにもなります。
▶うちが療育を決めた理由「発達が気になる息子と歩む日々」
まずは健診やかかりつけ医・地域の相談窓口へ
初めの一歩は、「相談できる場所を知ること」。
子どもの発達について相談できる窓口はいくつかあります。
たとえば:
- 地域の保健センターや子育て支援課
- 乳幼児健診(1歳半健診・3歳児健診など)での相談
- 小児科・耳鼻科などのかかりつけ医
- 発達相談を専門とする児童発達支援センターや療育センター
健診では、発達チェックの場面で「気になることはありますか?」と聞かれることもあります。
そのときに感じている不安をそのまま伝えることで、保健師さんや専門職がアドバイスをくれることも。
「相談=診断」ではありません。
「うちの子、ちょっと気になるんです」と気軽に話すだけでも大丈夫です。
早期に気づくことで、サポートの選択肢が増える
発達の違いに早く気づくことができると、必要に応じたサポートを受けやすくなります。
「療育」と呼ばれる支援や、子どもの特性に合わせた関わり方を学ぶ機会も増えます。
療育=特別な子が受けるもの、ではありません。
わが家も最初は「療育は必要?」と迷いましたが、実際に通ってみて感じたのは、
「親子で前向きに関われる時間が増えた」ということでした。
発達の悩みは、ときに「様子を見ましょう」で終わってしまいがち。
でも、早めに相談することで、その子に合った支援や療育につながるチャンスが広がるという大きなメリットがあります。
早期支援のメリット
- 子どもに合った関わり方がわかる
- 家庭でもできるサポート方法が見つかる
- 親自身が安心して育児できるようになる
息子の特性を知ることで、怒ったり悩んだりする時間が減り、気持ちにも少しずつ余裕が生まれました。
不安を一人で抱え込まず、誰かに話してみることが第一歩です。
「発達が気になるかもしれない」と感じた時点で、すでにあなたはお子さんのことをしっかり見ている、立派なサポーターです。
▶わが家が療育に通いはじめた理由と、そのメリット・デメリット
さいごに〜「うちの子らしさ」を大切にしながら〜
言葉の遅れや発達の違いに気づいたとき、親としては「なんとかしなきゃ」「うちの子だけ遅れているのでは」と焦る気持ちになることがありますよね。
でも、子どもたちはそれぞれ、自分だけのペースと個性をもって育っています。
たとえまわりと違って見えたとしても、それは「劣っている」わけではなく、
親が上手く教えられていないわけでもなく、育つペースがひとりひとり違うだけ。
私自身、息子の発達に不安を抱えていた頃、毎日がモヤモヤと心配の連続でした。
でも、相談先で話を聞いてもらい、息子の特性を理解することで、
「この子なりの見え方や感じ方があるんだ」と思えるようになりました。
それからは、「できないこと」ことばかりに目を向けるのをやめました。
「できていることをに目を向ける」「まだできないことだと知る」「何を考えているのかがわからないことがわかった」など、
『今の状態を受け止める』ことの大切さを感じています。
そして「できるようになったささいなこと」にしっかりと目を向ける。それが一番大事にしていることです。
もし今、不安を感じている方がいたら——
その気持ちを、どうかひとりで抱え込まないでください。
小さな心配を誰かに話すことで、見える世界が少し変わるかもしれません。
わが子のペースを大切に、無理せず親子で一歩ずつ進んでばいい。
子どもは昨日より今日、少しでも成長してくれています。